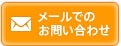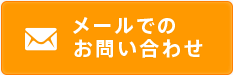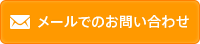遺言書が見つかった場合。検認とは?
被相続人が亡くなる前に自筆の遺言書を残していて、相続開始後にそれを見つけた場合、見つけた者はたとえ自分が相続人であっても、勝手に中身の確認をしてはいけません。というのも、見つかった遺言書は、原則、家庭裁判所にて「検認手続き」をしなければならないからなのです。
遺言書の検認には、遺言書の偽造・変造を防ぎ、そのままの状態で保存しておくという意味があります。見つけた者も、自ら開封したことによって偽造・変造を疑われてしまう可能性があるため、遺言書を発見した際は、迅速に検認手続きを取るようにしましょう。
検認は有効・無効を確認する手続きではない
なお、検認は遺言書の有効・無効を法的に確認するための手続きではありません。遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせ、遺言書の状態と内容を保存するために行われる手続きとなっています。よって、検認された遺言書が有効であるか、無効であるかについて相続人同士で争いがある場合、検認後に別の手続きによって有効か無効かが判断されることになっています。
ただし、遺言書が公正証書遺言であった場合は、検認手続きを経る必要はありません。公正証書遺言というのは、公証役場にて作成される遺言書の方式です。公正証書遺言はすでに公証人が立ち会い、役場にて内容の保存が行われているため、検認の必要がないというわけです。
検認手続きには何が必要?
では、検認手続きをするには、どういったものが必要になるのでしょう?
まず、検認手続きは家庭裁判所に申し立てをしなければ始まりません。申し立てをすべき立場にあるのは、遺言書の発見者、もしくは保管者となっています。相続人であれば誰でも良いわけではありません。
次に、検認に必要な書類として、「申立人の戸籍謄本」、「相続人全員の戸籍謄本」、遺言書の内容が事前にわかっていて(封がされていなかったなど)相続人以外に財産を譲り受ける者(受遺者といいます)の指定があれば、「受遺者の戸籍謄本」、そして、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」を集めなければなりません。
また、検認当日は印鑑を用意しておくと何かと便利なので持っていくようにしましょう。
検認の流れと検認後について
検認の申し立てがされると、相続人と受遺者に対して検認手続きが実際される日時が通知されることになります。検認当日は、参加者全員の前で遺言書の開封、内容と形状の保存、そして最後に検認調書という書面が交付され、手続きは終了します。なお、検認は参加してもしなくても、結果として検認調書が裁判所から送られることになっています。
検認後は、その遺言書どおりの内容で遺産分割をするか、または遺言書の有効・無効を争うか、のどちらかになります。どちらも相続人同士では揉めてしまう可能性がある手続きとなっていますので、可能であれば専門家に依頼をしたほうが良いと言えるでしょう。