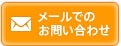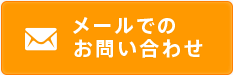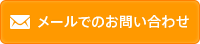相続放棄の手続き
相続放棄の申述は家庭裁判所で行わなければなりません。ただ単に、相続放棄をすると他の相続人に伝えれば良いわけではありませんので勘違いしないようにしましょう。
また、相続放棄の申述は、自分に相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。この期間をすぎると相続の単純承認(相続を受け入れること)があったとみなされ、相続放棄をすることができなくなってしまうので、必ずこの期間内に手続きを行うようにしましょう。
家庭裁判所に提出する必要書類
上記のように、相続放棄の申述は家庭裁判所で行います。その際は、必要書類の提出を求められることになりますので、事前に準備をしておかなければなりません。
主な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の死亡が記載されている住民票・または除票、相続人の戸籍謄本・住民票、といった公的な書類となっています。戸籍謄本であれば本籍地のある市区町村役場、住民票であれば住民届を出している市区町村役場からそれぞれ取り寄せることが可能です。これを3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄後の財産管理義務に注意
なお、いくら相続放棄をしたからといって、相続財産の管理義務がすぐになくなるわけではないので注意しましょう。わざわざ財産目録まで作って本格的に管理をする必要はありませんが、次の相続人が相続財産の管理を行える状態になるまでは、自身の財産と同様の注意力で管理を継続する必要があります。もともとは相続人である自身が相続放棄をしたことによって、後順位の者に相続権が移ることもありますし、相続人が誰もいなくなれば相続財産管理人が選任されることになります。こういった者に対して財産の引き渡しが完了するまでは、いくら相続放棄をしたとはいえ、相続財産を野放しにしてしまわないように注意してください。
相続放棄の取り消しはできない点に注意
その他にも、相続放棄には注意しなければならないことがあります。
それは、原則として、相続放棄は後から取り消すことができないという点です。例外として、他の相続人がついた嘘など(詐称行為といいます)によって、相続放棄をしてしまった場合などは、騙されたことに気付いてから6ヶ月以内であれば取り消しが認められることがあります。しかし、こういった特別な事情がない場合、相続放棄を取り消すことはできません。よって、相続を知ってから3ヶ月という期間はじっくり検討する期間という意味で、熟慮期間と呼ばれています。取り返しのつかないことにならないように、熟慮してから相続放棄を行うようにしましょう。