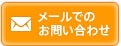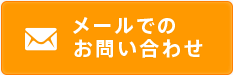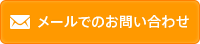相続財産の取り扱い(共有されるものとされないもの)
被相続人が亡くなった後、残された財産を法律では「相続財産」と言います。相続財産は相続開始後、遺言書でも残されていない限り、原則として相続人同士で共有をしていることになっています。この共有状態を遺産分割協議によって、それぞれの相続人に分割することになります。
しかし、すべての財産が共有されるわけではありません。では、どういった相続財産が共有されることになり、また、共有にはどのような意味があるのか?共有されない財産にはどのようなものがあるのか?といったことを、今回は詳しくご説明していきます。
共有ってどんな状態?
共有というのはまさに言葉のとおり、1つのものを複数人で所有している状態のことです。しかし、この共有という状態は、法律的に見るとかなり面倒な状態となっています。
というのも、被相続人が不動産を所有していたとなれば、相続が開始した時点で、その不動産は相続人全員の共有状態となります。
もちろん名義などは変わっていませんが、相続の開始は被相続人が亡くなった瞬間となっていますので、たとえ遺産分割協議や名義変更が終わっていなかったとしても、相続自体は開始しているのです。これだけ聞いてもさして問題があるように感じませんが、不動産が共有となっている場合、共有者(つまり相続人)全員の意思が合致しないと、売却といった処分行為をすることができません。つまり、共有状態が解消されない限り、一つの相続財産全体に手をつけることができないということです。
共有の権利は手放すことが可能
法律では、ある財産を共有しているとき、その共有者は「共有権(持分権)」を持っていると表現されます。この共有権に限っていえば、他の相続人の意思に関係なく手放すことが可能となっていて、もちろん売却することも可能です。
しかし、共有権を手放すということは、その手放した共有財産については遺産分割に参加する権利を失うことになりますので注意しましょう。
なお、共有権を手放すといっても、同じ相続人に対して譲り渡すならまだしも、まったくの第三者に譲り渡した場合、遺産分割協議に赤の他人が参加してくることになり、余計に相続問題がややこしくなってしまいかねません。よって、こういったことがないように、しっかりと遺産分割協議を終えてから処分を検討するようにしましょう。
共有されない相続財産とは
上記のように、共有される財産の代表例は不動産です。では、共有されない相続財産にはどういったものがあるのでしょうか?その代表としては、金銭債権、つまりは預貯金があります。
被相続人が残した預貯金は、共有されない相続財産になりますので、たとえ遺産分割協議をしていなかったとしても、相続の開始によって自分の相続分については個別に払い戻すことが可能となっています。
しかし、実際には銀行側が後にトラブルが発生することを懸念し、相続人全員の合意がない場合は、払い戻しに応じてくれない可能性が高いというか殆んどだといって良いでしょう。つまり、相続財産の取り扱い方としては、共有されていてもいなくても、遺産分割協議によってそれぞれの相続分を確定させてから手をつけるに越したことはない、ということをよく覚えておきましょう。